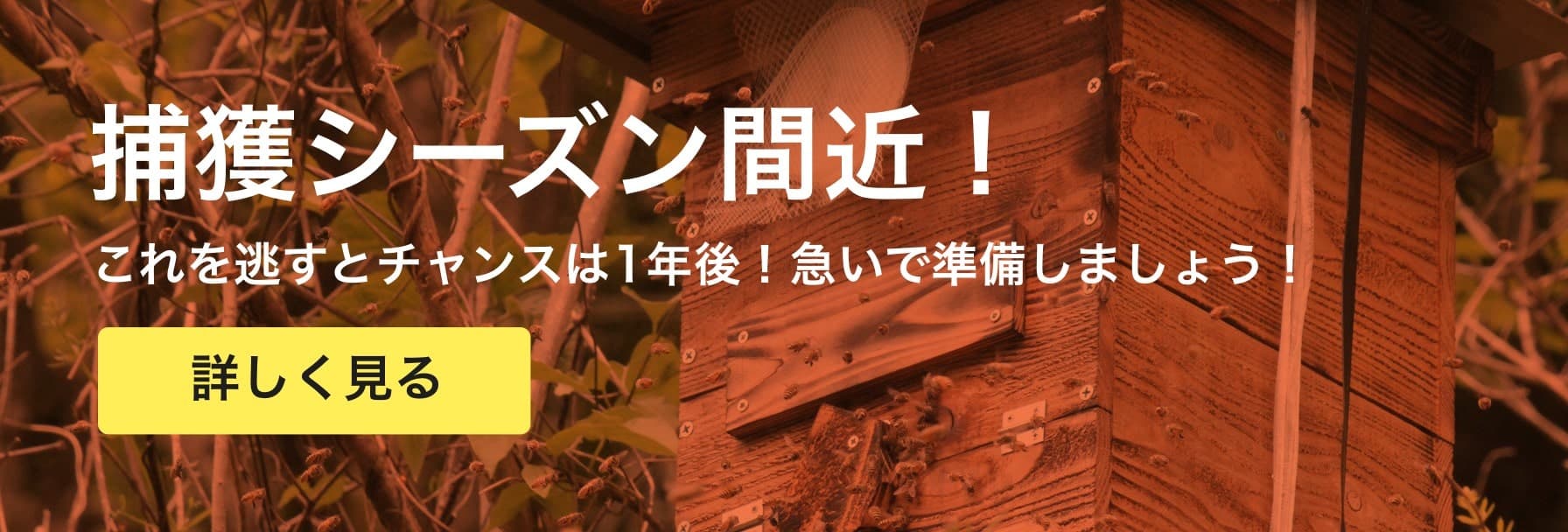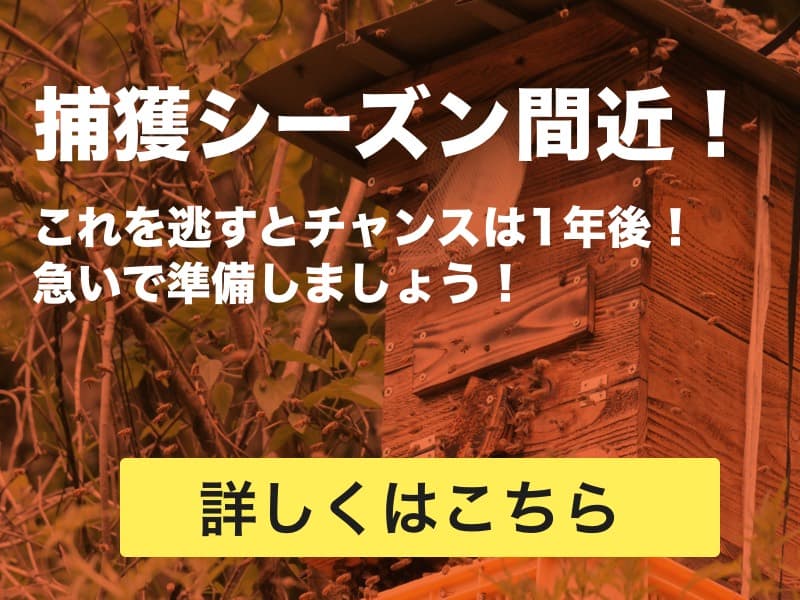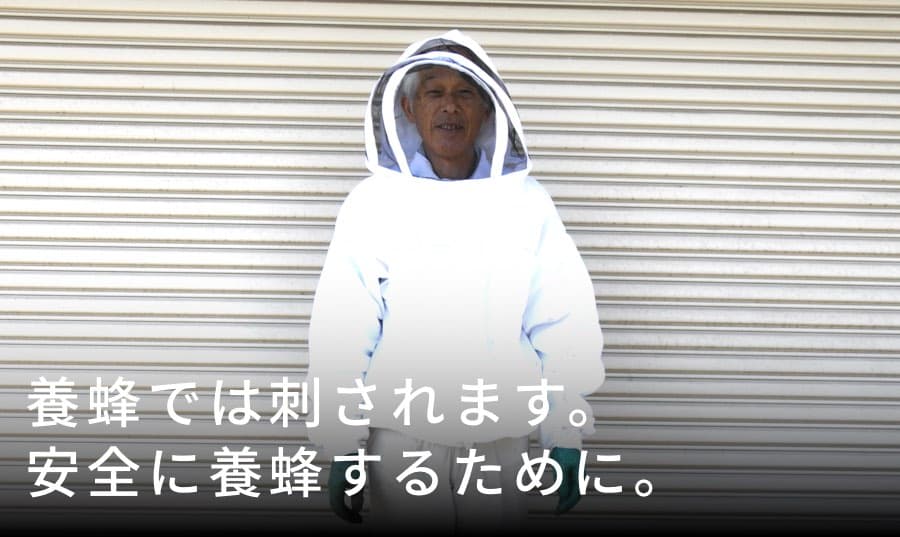ニホンミツバチを趣味で飼育する場合も、養蜂振興法に基づき届け出が必要です。以前はニホンミツバチの趣味の飼育については必要ありませんでした。平成 24 年 6 月に養蜂振興法が一部改正され、平成 25 年 1 月 1 日に施行されました。
養蜂振興法とは
農林水産省のホームページには、 「蜜源をめぐるトラブルの発生防止、適切な飼育管理による蜂病のまん延防止等が重要な課題となっています。このため、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るために、、、」と少々難しい説明がされています。
簡単に言うと、飼育者が同じ場所に集中するとミツバチたちが花の蜜を奪い合うため、ハチミツの生産量が減ります。養蜂業者にとっては大きな問題となりトラブルにつながります。養蜂業者がそれぞれ飼育数と場所を申告し、必要に応じて配置場所か数を調整します。
また、ミツバチの病気の対策も大きな目的の一つです。病気の検査を行い、万が一発生したときには蔓延を防ぐために情報を飼育者に伝えるために、行政がミツバチの飼育情報を把握しておく必要があります。
こういった目的から、以下のような項目を法律で定めています。
- 蜜蜂飼育者の都道府県に対する届出義務
- 転飼養蜂(県域を越える蜂群の移動)の許可制
- 蜜蜂の適正な管理
- 蜜源植物の保護増殖の努力義務
ニホンミツバチであっても、セイヨウミツバチであっても、この法律に従う必要があります。
また、運用については、都道府県で違いがありますので、直接窓口に確認するようにしてください。
趣味のニホンミツバチでも必要
以前は、業ではなく、趣味で飼育する場合なら届け出は不要でした。
平成 24 年 6 月に改正された養蜂振興法が平成 25 年 1 月 1 日に施行され、趣味での飼育も飼育届が必要になりました。そのため、趣味で飼育されていたニホンミツバチも飼育届が必要になりました。
ただし、都道府県によって対応が大きく異なり、ニホンミツバチを重箱式巣箱のようなシンプルな巣箱で飼育する場合は、その後も届出が不要な県もありました。
しかし、令和 5 年 11 月の農林水産省の通知により、そのような例外を認めず、基本的に届出を実施していくという方向性が示されました。
昔からニホンミツバチを飼育されている方の中には、届け出が不要と思っておられる方もいるかもしれませんが、改正後はニホンミツバチでも飼育届が必要になっています。違反することのないように気をつけてください。
飼育届の窓口は各都道府県
飼育届の窓口は、自分が住んでいる都道府県を通して行います。各都道府県が窓口を用意しています。「みつばち飼育届京都」などのように、都道府県名と一緒に調べてください。
例えば、京都府では次のページで飼育届の方法を解説しています。 蜜蜂飼育届の提出について| 京都府
例えば、弊社の活動地域では、住所地の市役所、町村役場を通じて行なうことになっています。1 月 31 日までに、年内に飼育を予定している人も含めて飼育届を出す必要があります。
飼育届の提出期限
飼育届は、毎年 1 月 31 日までに提出する必要があります。届出には、1 月 1 日時点での飼育状況と年間の飼育計画を記載します。
新たに養蜂を始める場合は、飼育開始前または開始後すみやかに届出が必要です。春に分蜂群を捕獲して養蜂を始める方は、捕獲後なるべく早く届出をしましょう。
具体的な期限は都道府県によって異なるため、窓口に確認することをおすすめします。
記入は難しくありません。各都道府県のホームページでは、飼育届の様式と記入例をダウンロードできます。わからない点があれば、窓口に電話で相談すれば丁寧に教えてもらえます。
飼育場所についての条例やルールについても合わせて確認する必要がありますので、飼育届の窓口に必ず問い合わせてください。
趣味の飼育が許可されないことはある?
法律の目的として、蜜源の適切な管理がありますので、他の人によってミツバチが設置されている場所の近くに巣箱を設置しようとした場合は、当事者同士で調整することになります。
セイヨウミツバチの場合は厳密に調整を行なっているところが多いのですが、ニホンミツバチを自宅周辺で数群れ趣味で飼育する場合、調整が必要となるケースは稀です。
しかし、こちらも地域によって大きく状況が異なります。特に、養蜂が盛んな地域では、趣味で飼育する場合でも他の養蜂家さんとの調整が必要になる場合があります。
実際に、弊社が運営しているミツバチQ&Aでも、飼育が認められないという相談が投稿されることがあります。
条例も確認しましょう
都道府県や市町村がミツバチの飼育について定めている場合があります。
有名なのは、大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例です。蜜蜂の巣箱の設置場所について、住宅や学校、道路などから一定の距離を離すことが定められています。
ミツバチの飼育届を出す際の窓口で担当者に聞いたり、インターネットで自分の住む行政区のルールを調べてください。
マナー、モラルを守ろう
養蜂によって起こりうるトラブルは多岐にわたります。
ミツバチの糞害は、洗濯物や車、家の外壁に茶色い汚れを残します。巣箱の周囲数十メートルの範囲で発生することがあり、隣家の洗濯物を汚してしまえば大きな問題になります。
また、春の分蜂シーズンには、数千匹から数万匹のミツバチが一斉に飛び立ちます。ミツバチとスズメバチの区別がつかない方も多く、「危険なハチを飼っている」と誤解されたり、市役所や警察に通報されることもあります。2019 年には恵比寿でミツバチの騒動がニュースで報道されたこともありました。
マナー、モラルを守ることは、法律を守る以前の問題です。特に、住宅が近い地域で養蜂される方は、十分に気をつけてください。
マナーを守らない飼育者が増えると、養蜂を制限する法律ができる可能性もあります。ニホンミツバチの飼育での近所迷惑については次のページで紹介しています。
近所トラブル対策
住宅地での養蜂はトラブルにつながります。苦情だけではありません。ニホンミツバチで起こりやすい近所トラブルと防止方法を紹介します。