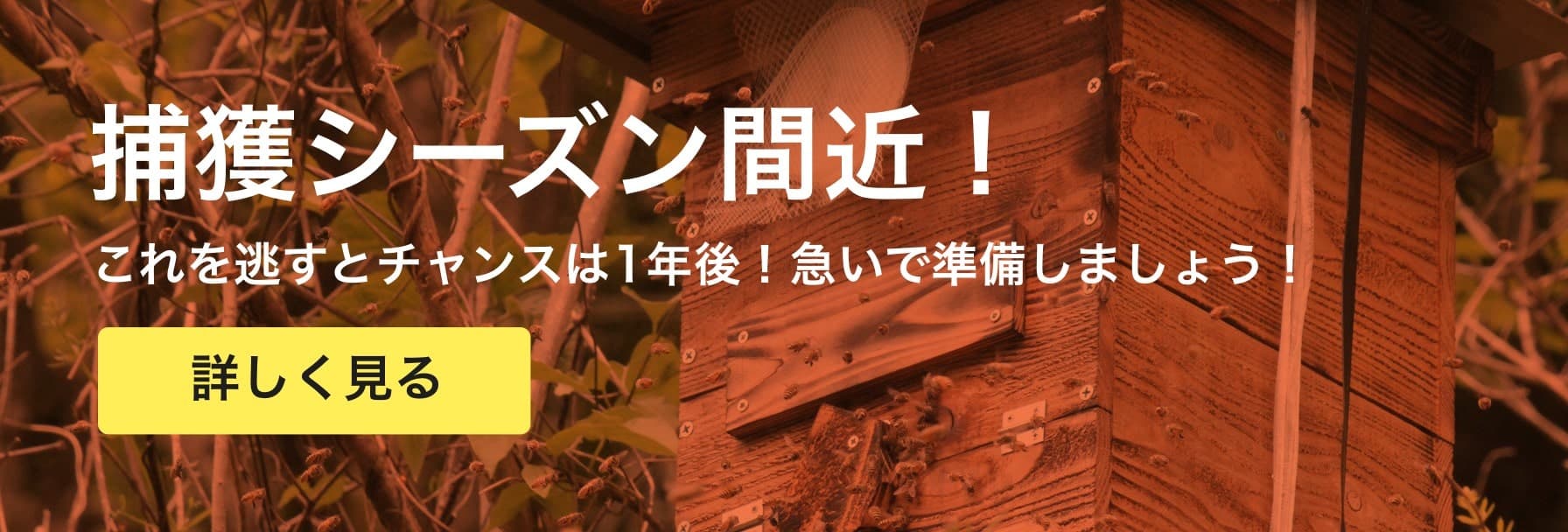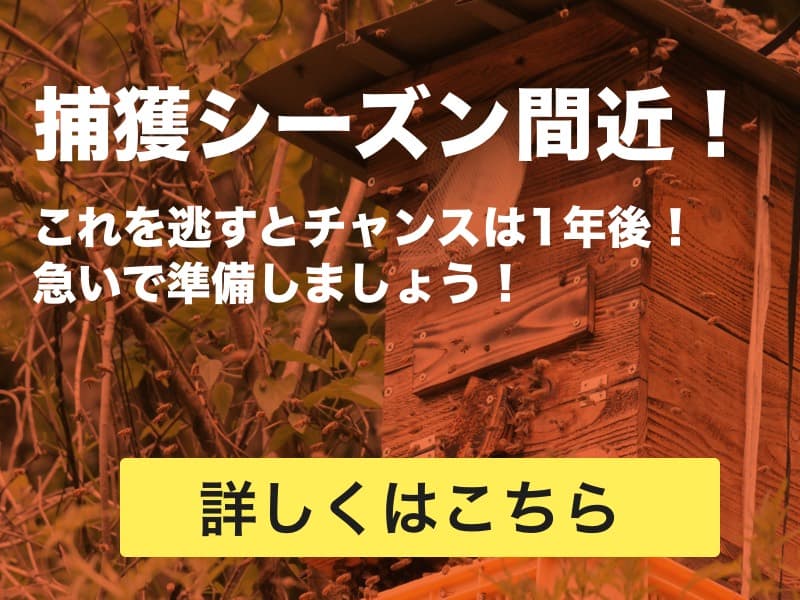ハチミツの採取は、捕獲に並ぶ大きなイベントです。ニホンミツバチを殺さずに、短時間で、効率的に採蜜を行っています。このページでは動画を使って採蜜の方法を紹介します。

重箱式巣箱の採蜜の仕組み
重箱式巣箱の採蜜は、ハチミツの貯蔵域以外を破壊しないという特徴があります。
ニホンミツバチの巣は、巣の上側がハチミツを貯める部分で、下側が幼虫を育てる部分になっています。
巣が大きくなって、重箱式巣箱が 4 段、5 段と積み重なったときの最上段は、ハチミツを貯める貯蜜域となっています。そこで重箱式巣箱では、最上段を取り外すことで採蜜を行います。
幼虫を育てる部分は採蜜によって破壊されることがないので、ニホンミツバチはそのまま生活を続けることができます。
最上段を切り離す方法について、動画で紹介しています。
もちろん、ハチミツが減ってしまいますが、ニホンミツバチは働き者なので、冬越しに必要な量よりも多く蓄えています。冬越しに必要な分を残しておけば問題はありません。
重箱式巣箱では、だいたい年に1回採蜜します。ハチミツを多く集める群れでは、何度も採蜜できることがありますが、反対に1回も採れないことも珍しくありません。
採蜜時期は主に秋
私たちは、春に捕獲した群れであれば、秋まで待って採蜜を行います。冬を越えた 2 年目以降の群れも基本的には秋に採蜜しますが、大きな群れの場合は夏に入る前に採蜜することもあります。
採蜜の時期について質問を受けますが、ハチミツの貯まり具合によるので、一概にこの時期に採蜜するとは答えられません。
気候や蜜源に加えて、その年の春に捕獲した群れか、越冬した群れかによっても変わります。
平均的な群れなら秋の採蜜となります。蜜源が豊富であれば、春の捕獲群から初夏の採蜜も可能ですが、かなり稀です。
反対に蜜源が少なければ、1 回も採蜜できないこともあります。これは珍しくありません。
春に捕獲した群れのハチミツを夏前に採ることは滅多にありません。
早めの採蜜は失敗の元
巣がまだ小さいうちに、重箱式巣箱の最上段を取り除くと、巣を支えている大部分がなくなってしまい、巣が落下してしまいます。これを巣落ちと呼びます。巣落ちすると、ほとんどの場合は逃亡するか、消滅してしまいます。
巣落ちしないまでも、巣が成長していないため育児域まで取ってしまったり、採蜜後の逃去の危険性も高くなります。
採蜜には失敗のリスクもあります。楽しいイベントが一転し、後悔が残る結果になることもあります。
これは初心者にはよくある失敗です。早く採蜜したいという気持ちは分かりますが、巣の成長をしっかり確認してから採蜜しましょう。
採蜜の前に、これから説明する注意点をしっかり学んでから行ってください。
巣の大きさを必ず確認
採蜜の前に、巣がどこまで成長しているかを巣箱の底から写真を撮って調べます。
巣が十分に大きくなっていないうちに採蜜すると、巣落ちしてしまうことがあります。早めの採蜜は失敗の元です。
採蜜を始める前に、しっかりと確認しておく必要があります。
重箱式巣箱では、次のように底から覗き込んで巣の大きさを確認します。
私たちの巣箱は、巣の中の様子をデジカメで下からフラッシュ撮影できるようになっています。

次の写真のような場合、巣が巣門付近まで達していることが分かります。

私たちの巣箱では、4 段以上がいっぱいになれば採蜜できます。ただ、群れが多いと採蜜や継ぎ箱だけでも大変なので、6 段まで重箱を積んでおいて秋に点検し、1 段分または 2 段分採ることが多いです。
これは重箱式巣箱の寸法によっても事情が変わってきます。私たちの巣箱の作り方や寸法等は、重箱式巣箱の作り方をお読みください。採蜜のタイミングについては、全国の愛好家が集まるミツバチQ&Aで巣箱や群れの状況の写真を添付して質問してください。
1. フタを取り外す
重箱式巣箱の採蜜では、一番上の箱を分離します。
まずは、屋根やフタなどの上部を取り外します。スノコが内側にあるため、フタの部分には直接巣がついていません。このためフタは簡単に外すことができます。

フタを外すと、たくさんのミツバチがスノコの上にいます。息を吹きかけたり、扇風機で風を送ったり、スノコを軽く叩いて振動を与えると、周囲に飛び出したり、巣箱の下側に移動してきます。
そんなことをするとニホンミツバチが一斉に襲ってくるのではと心配になりますが、最上段にいるニホンミツバチは驚くほど大人しいので大丈夫です。
なぜこんなにも大人しいのでしょうか。働き蜂は、羽化してからしばらくの間、掃除や幼虫の世話、ハチミツの製造などの安全な仕事をしており、羽化してから一定期間経った後に、巣門の警備や花の蜜を集める危険な仕事をするようになります。
最上段にいるニホンミツバチは、巣箱の中の仕事をしている働き蜂です。外に出ることがないので、外敵に遭遇することもなく、攻撃性が低いのでないかと私たちは考えています。
反対に巣門付近で警備の仕事をしている働き蜂は攻撃性が高いので、採蜜中に刺されないように注意してください。
スノコの上の働き蜂を移動させると、スノコの隙間から、巣を直接見ることができます。
巣が下まで伸びてきていても、上部にハチミツが貯まっていない場合があるため、貯蜜量を確認します。
巣房にフタが作られている部分に、完熟のハチミツが貯められています。フタはされていないものの、巣房に液体が入っている部分には、製造中のハチミツが貯められています。
製造中というのは、水分が多い状態のハチミツです。私たちは、目安として全体の 8 割以上の巣房にフタがされていれば、採蜜を行っています。それほどハチミツが貯まっていない場合は、しばらく日数が経ってから採蜜を行います。
2. スノコの板を取り外す
まず、スノコの木ネジをドライバーで取り外します。
ちなみにこのスノコは、採蜜をスムーズに行うために大変重要です。

私たちの巣箱の作り方や寸法等は、こちらをご覧ください。
重箱式巣箱の作り方
ニホンミツバチの重箱式巣箱の作り方を図解と動画で解説。オオスズメバチ対策の巣門サイズなど、捕獲成功のポイントも紹介します。

スノコには、巣が付いているので、木ネジを外しただけでは取れません。
そこで、ワイヤーを重箱とスノコの間に通すことで、スノコを取り外します。
ワイヤーを使う前に、ヘラを使ってスノコと重箱の間に隙間を作っておくと作業しやすくなります。

スノコを取った後は、最上段の巣と巣の間にいるニホンミツバチを、巣箱の上から風を当てることで下の段に移動させます。
最上段にはまだたくさんのミツバチがいます。
このまま最上段を取ってしまうと、ミツバチが巣箱内へ残ったままになってしまいます。
このため、風や振動を加えて、下の段に移動してもらいます。
3. 最上段を分離する
最上段からニホンミツバチがいなくなったら、最上段を切断します。スノコと同様に、重箱と重箱の間にヘラを通すことで隙間を作ります。その後、ワイヤーを使って最上段を切断します。

切断した最上段を入れる箱を用意しておいてください。
私たちは、食品用の大きなタッパーを利用しています。この中にステンレス製の台を入れておき、重箱がタッパーの底から 5cm 程度高くなるようにします。こうすることで、たれ落ちたハチミツが重箱で汚れないようにします。
このタッパーに入れたまま持ち帰り、巣からハチミツを取り出します。
4. たれ蜜を採る
まず初めに、たれ蜜を採ります。たれ蜜とは、重力で自然と落ちてくるハチミツを指します。後で説明する、巣を圧縮して取り出すハチミツと比べて、巣のカスや花粉などが混ざりにくいため透明度が高く、品質の高いハチミツであるとされています。
切り取った重箱の上側が上になるようにタッパーに入れて、巣板を 3 枚におろすようにナイフで切れ目を入れます。次に、重箱をひっくり返して下側からも切れ目を入れます。先ほど述べたように重箱の底はタッパーの底から浮かしてあり、たれ落ちたハチミツが重箱で汚れないようになっています。
ゴミが入らないようにタッパーにフタをして1晩放置しておくと、重箱の中のハチミツのうちの約 7 割が落下します。1 箱にはおおよそ 5kg のハチミツが貯まっているので、そのうちの 3.5kg はこのように取り出すことができます。重箱とステンレス製の器具を取り出すと、ハチミツだけがタッパーに残ります。
そのまま巣蜜で味わうことも
たれ蜜を採る前に、そのまま巣を切り取って巣蜜を食べることもできます。
ニホンミツバチの巣は、食べても無害な蜜蝋(みつろう)という物質でできています。そのままパクッと食べることができます。
このような巣蜜は販売されていることもありますが、外国産のものが多く、国産のものでもセイヨウミツバチのものです。
ニホンミツバチの巣蜜はまず販売されていない大変希少なものです。次の動画では巣蜜を作り、色々な方法で食べています。
5. ハチミツを圧搾する
残った約 3 割のハチミツは、巣を圧縮して絞ります。まず、巣板をミカンの袋のような目の粗いナイロン製の袋に入れます。これは、巣がバラバラになることを防ぐためです。布などの目が細かい袋に入れると、ハチミツが袋から出てきにくいので注意してください。私たちは、玉ねぎ用のナイロンの袋を使用しています。
巣を袋に入れたらそのまま押しつぶします。私たちは、1 年で 100 回近く採蜜を行うので、作業時間を短縮するために圧搾機を使っています。
しかし、圧搾機を購入する必要はありません。巣を押しつぶすことができれば何を使っても大丈夫です。台所にある器具や手を使って巣を押しつぶしてください。
6. ハチミツの濾過の方法
以前は木綿の布でろ過していましたが、現在は Amazon などで売られているナイロンメッシュ素材のハチミツ用ネット(円錐型)を利用しています。
ナイロンメッシュは穴に詰まったゴミも取りやすく、水洗いしてもすぐに乾きます。ろ過した後のハチミツをしばらく置いておくと、表面に細かい粒が浮いてくることがあります。
このような細かい巣のかけらや花粉は人体には影響がありませんので、自家消費用の場合は問題ありません。
気になる場合は、浮いてきた粒を除去したり、より細かい網でろ過してください。
絞りカスから蜜蝋を作る
ハチミツを取り除いた後は、絞りカスから蜜蝋を作ります。
蜜蝋の作り方
ニホンミツバチの搾りカスから蜜蝋を作ることができます。湯煎する方法やホットプレートを使う方法など複数の蜜蝋の作り方を紹介します。