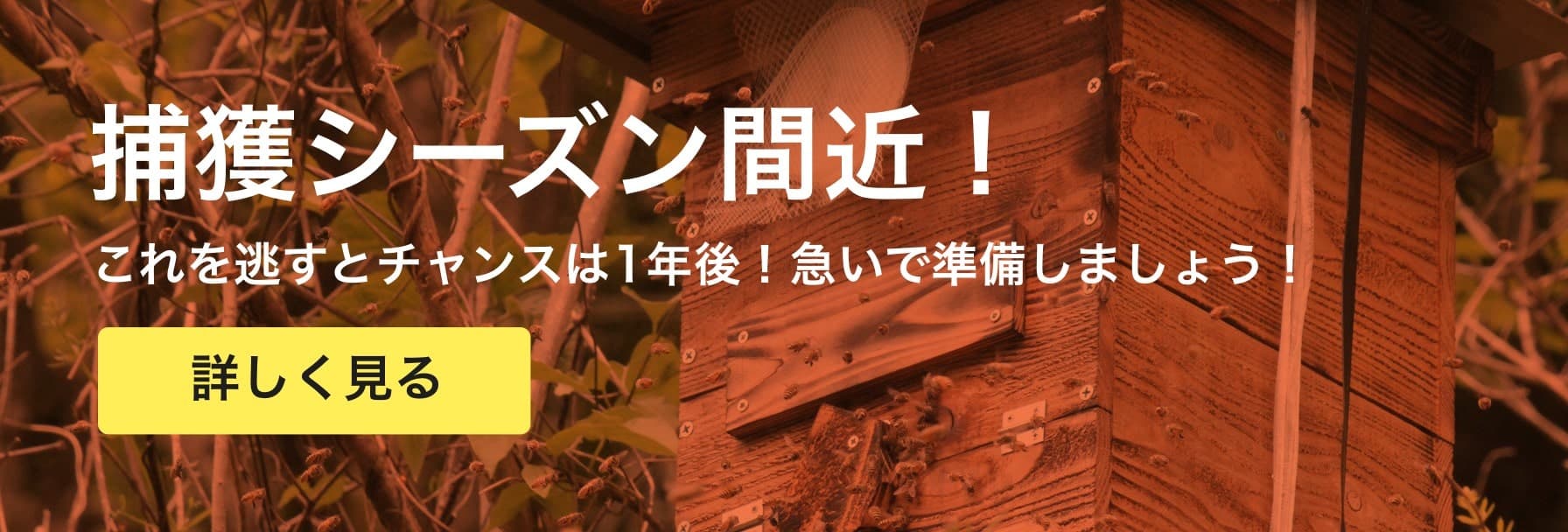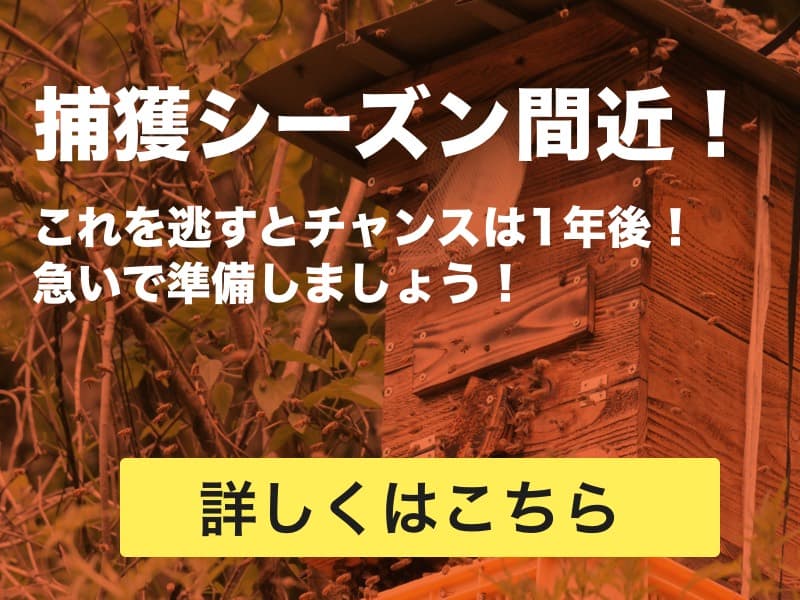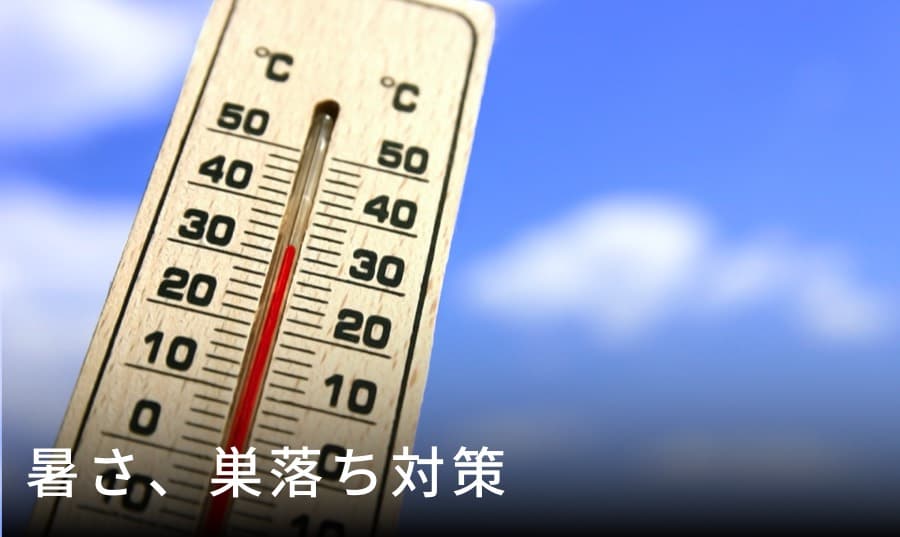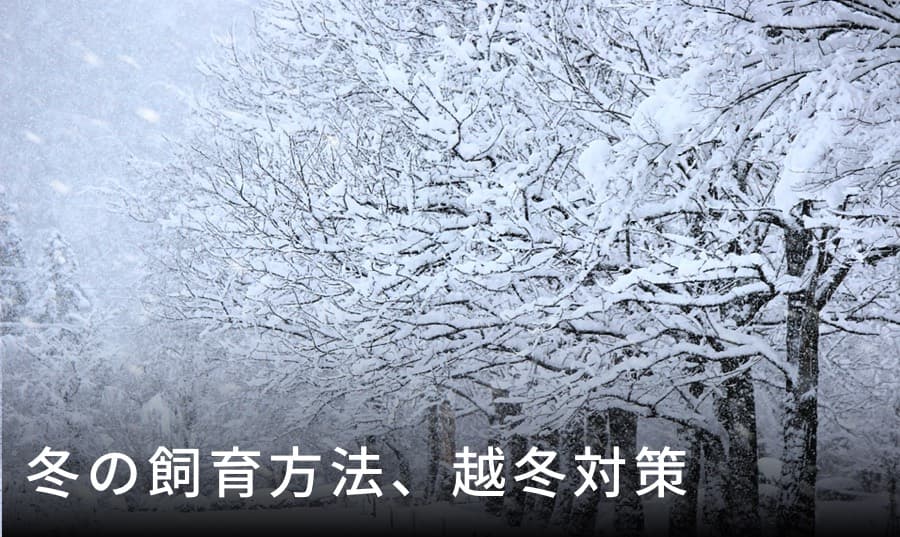ようやくニホンミツバチを捕獲できたら、飼育が始まります。重箱式巣箱で飼育する場合、普段やることはほとんどありません。
春捕獲してから、ニホンミツバチの飼育が始まる
春に群が捕獲できたら、ニホンミツバチの飼育が始まります。まだ捕獲できていない方、これからニホンミツバチの飼育を始めようと考えている方向けには、ニホンミツバチの捕獲方法を詳しく紹介しています。まずは、次のページをご覧ください。
飼育を始めたい方へ
ニホンミツバチの飼育を始めたい方のために、どのように、いつ準備すれば良いのかや、必要な準備物などを紹介します。週末養蜂家になりたい方はまずはこの記事を読んでください。

最初は、巣箱の上の隅の方にニホンミツバチが固まっています。ニホンミツバチは一から巣作りを行います。次の動画は 2 週間後のニホンミツバチの様子です。
群れや、周りの環境によって、巣を作る速さは大きく異なります。
基本的に放置するため、「巣箱」が重要
重箱式巣箱の飼育の場合、人間がすることは特にありません。そもそも、重箱式巣箱は人間が蜂を管理するために使うものではなく、私たちはそういう目的で用いるものではないと考えています。
野生のミツバチが勝手に巣箱に住み着いている状況なので、人間ができることは限られています。快適に、安全に暮らせる巣箱を提供することが最も大事です。
巣箱が悪ければ、ベテランの飼育者でもうまく行きません。外敵に強く、耐久性、断熱性が高い巣箱を使いましょう。巣箱については次のページで紹介しています。
重箱式巣箱の作り方
ニホンミツバチの重箱式巣箱の作り方を図解と動画で解説。オオスズメバチ対策の巣門サイズなど、捕獲成功のポイントも紹介します。

巣箱の中を覗いて点検を行う
重箱式巣箱では、巣箱を底から覗いて内部の様子を点検します。健全な群れでは、巣板が見えないほど、たくさんのニホンミツバチがいます。
次の群れでは、ニホンミツバチの数が少なく、巣の半分程度が露出しています。これは健全な状態ではありません。この群れは女王蜂がいなくなっており、この後に消滅してしまいました。
巣板が見えているときは、何らかの問題を抱えている可能性が高いです。写真を撮ってミツバチ Q&A で質問してください。全国の先輩からアドバイスをもらえます。
巣の成長速度や調子の良さ・悪さは分かります。それによって、次に巣箱を追加する時期や、採蜜のタイミングを考えることができますが、調子が悪い群れに対して、有効な対策を行えるとは限りません。
巣が大きくなってきたら、重箱を一番下に足す
待ち箱では 2 段の重箱式巣箱を使います。分蜂群が入居すると、巣が上から下へ伸びていき、秋までに 4 から 5 段(高さ 60 から 75cm) 程度の空間が必要になります。
2 段分いっぱいまで巣が伸びるには 1、2 ヶ月かかりますが、捕獲したら早めに追加の重箱の用意をしておきましょう。
入居して数週間で巣がある程度大きくなり群れも安定するので、その頃に継ぎ箱をしてください。巣が成長すると巣箱全体が重くなり、継ぎ箱が大変です。
巣の成長に合わせて 1 段ずつ追加する必要はありませんので、この段階で採蜜まで可能な 4 段まで追加することをおすすめします。
重箱を追加する時期が遅れてしまうと、巣が下にはみ出してしまい、巣門枠や台の部分まで巣ができてしまいます。また、巣がはみ出なくても、蜂が巣の下の方に集まってくるので持ち上げにくくなります。
次の動画は継箱のタイミングが遅れて巣がはみ出てしまっている悪い例です。幸い、持ち上げ機を使ったため問題になることはありませんでしたが、手で継ぎ箱することは困難です。
夏は暑さに注意
ニホンミツバチは日本の気候に適応した在来種ですが、年々気温が高くなっており、暑さ対策の重要性が増しています。
ニホンミツバチは、もともと森の中の木などに巣を作る場合が多いです。森や木があるところは涼しいですし、木の中は涼しい環境です。暑い日に林や神社などにいくと、涼しく感じるのではないでしょうか。しかし、巣箱を民家の周辺や畑に置くことが多いので、暑さの対策が重要になります。
暑くなるとニホンミツバチが外へ涼みに出てくることもありますが、より深刻なのは巣落ちです。暑さで巣が柔らかくなり、重さに耐えられなくなった巣が丸ごと落下してしまうのです。
巣落ちの原因は、巣箱の設置場所だけでなく、巣箱の構造が原因となることが多いです。暑さ対策について詳しくは次のページをご覧ください。
暑さ・巣落ち対策
ニホンミツバチの巣落ちは暑さが原因で起こります。日陰への設置、遮光、適切な板厚の巣箱、夏場の採蜜を避けるなどの対策で巣落ちは防げます。
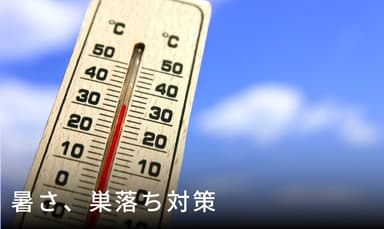
対策が必要な外敵
ニホンミツバチには様々な外敵がいますが、群れを壊滅させるような外敵は、オオスズメバチ、熊、アカリンダニです。
オオスズメバチは土の中に巣を作るスズメバチです。このため山間部や自然が豊かな場所の方が多く生息しています。オオスズメバチの被害は、巣箱の構造を工夫することでほとんど防ぐことができます。詳しくは次のページをお読みください。
スズメバチの対策
スズメバチの中でも、キイロスズメバチはニホンミツバチの巣箱に頻繁にやってきます。オオスズメバチは世界最大のスズメバチで、ニホンミツバチの群れを全滅させることもあります。

山間部で熊が出没する地域では、必ずと言って良いほど熊が巣箱を襲いにやってきます。費用はかかりますが、電気柵で被害を防ぐことができます。詳しくは次のページをお読みください。
熊対策
熊(クマ)は養蜂家の大敵。巣箱を破壊しハチミツと蜂の子を奪います。電気柵による対策や、被害が出やすい時期と場所について解説。

アカリンダニは全国的に大きな被害を出しているダニです。
アカリンダニ
アカリンダニはミツバチの気管に寄生する外来ダニで、2010年に日本で初確認されました。徘徊、Kウイングなどの症状や検査方法について解説します。

また、スムシというミツバチの巣を食べてしまう蛾の幼虫も天敵としてよく挙げられます。しかし、スムシで群れが消滅するのではなく、なんらかの原因で弱った群れにスムシが繁殖します。そのため、スムシは直接的な原因ではない場合がほとんどです。
スムシについても解説しておりますので、詳しくは以下のページをお読みください。
スムシの対策
スムシはニホンミツバチの巣を食べる蛾の幼虫です。繁殖すると対処が困難になるため予防が重要。強い群れを維持し、巣箱構造を工夫することで被害を軽減できます。

台風シーズンには巣箱の転倒に注意
台風シーズンには毎年、重箱式巣箱が転倒してしまった事例が報告されています。巣箱が転倒するとその衝撃で巣板が落下したり、女王蜂が事故死したりと、致命的な危機となります。
最近では、台風以外でも大雨や強風が吹くことも増えています。早いうちから転倒対策をしておきましょう。
弊社では、台から屋根までをロープでしっかりと縛っています。そして、重心を低くするため台の部分にコンクリートブロックで重りを載せています。この対策により、まず転倒は発生しませんが、弊社が飼育を行なっている京都府はそれほど強い台風が来ませんので、暴風が警戒される地域ではより万全な対策を講じてください。
ハチミツが貯まれば採蜜を行う
ハチミツが貯まれば採蜜を行うことができます。主に秋に行います。
ただ、採蜜には失敗のリスクもあります。楽しいイベントが一転し、後悔が残る結果になることもあります。
巣がまだ小さいうちに、重箱式巣箱の最上段を取り除くと、巣を支えている大部分がなくなってしまい、巣が落下してしまいます。これを巣落ちと呼びます。巣落ちすると、ほとんどの場合は逃亡するか、消滅してしまいます。
これは初心者にはよくある失敗です。早く採蜜したいという気持ちは分かりますが、巣の成長をしっかり確認してから採蜜しましょう。
採蜜方法については次のページで詳しく解説しています。
採蜜方法
ニホンミツバチの採蜜時期は主に夏から秋。重箱式巣箱の最上段を切り離し、たれ蜜と圧搾でハチミツを収穫する方法を動画付きで解説します。

冬は群れの消滅の危機
ニホンミツバチは巣の中で 1 つに固まり、ハチミツを消費しながら厳しい冬を耐えます。ハチミツがなくなってしまうと餓死してしまいます。越冬のポイントは、十分な蜂蜜を残しておくことです。
冬に入るとミツバチの活動も低下するので、冬に入るまでの準備が重要になります。越冬方法について詳しくは次のページをご覧ください。
冬の飼育方法
冬の気温の低い日にはニホンミツバチは外に行かずに、ハチミツを消費しながら過ごしますが、飢えて群れが全滅することもあります。冬の飼育方法について紹介します。冬に入るまでの準備が重要です。

あくまで自然任せの飼育方法
これまで述べたように、重箱式巣箱の飼育は、シンプルな箱にニホンミツバチが住み着いただけの状態です。手間はかからないという長所の一方で、管理には限界があります。
ネット上では様々な手法が紹介されていますが、実際にはほとんど影響がないものも多いです。特に「こうすれば ○○ は防げる」「×× の対策は完璧」などという極端な主張には注意してください。
思い思いの工夫をして楽しむこともニホンミツバチの魅力の 1 つですが、初心者はそういったものに惑わされず、基本を疎かにしないことが大切です。
ミツバチに色々としてあげたい、しっかりと管理したいという方は、飼育に慣れてきた段階で巣枠式巣箱を使う手もあります。
過去には、ニホンミツバチは巣枠式巣箱では飼育できないと言われていましたが、色々なタイプのものが開発されています。ミツバチQ&A でも多くの方が情報を交換されています。
1 カ所で多数飼育するのは NG
生き物にとって最も大切なのは、十分な食料です。これはニホンミツバチにも当てはまり、彼らの食べ物である蜜や花粉が不足すると群れに問題が生じます。
エサ不足は、一カ所に多くの群れを飼うことで起こり、群れ同士で食料の奪い合いが発生します。また、セイヨウミツバチも含めた周囲の群れの密度にも影響されます。狭い範囲での多群れ飼育は、蜜や花粉の不足、ハチミツの減少、健康問題を引き起こします。
周囲の蜜源の量や他のミツバチの存在を把握するのは難しいため、初めは一群れのみを置いてください。群れの成長も早く、ハチミツが貯まる場合には群を増やす余裕があると言えます。よほど条件が良い場所を除くと、1 カ所では数群が限界です。
群が過密にならないように、移動を行なって配置を調整します。群れの移動については、次のページで紹介しています。
巣箱の移動方法
ニホンミツバチの巣箱を移動させる正しい方法を解説。30cm以内か2km以上の移動が基本です。入居当日なら自由に移動可能。重箱式巣箱の巣落ちを防ぐコツも紹介。

群が増えてくると最も重要なのが分散して設置することです。弊社では基本的に1カ所で1群れ飼育しています。特にハチミツが採れる場所では2群れ飼育します。